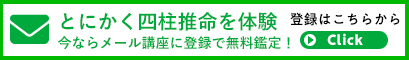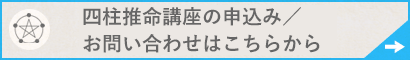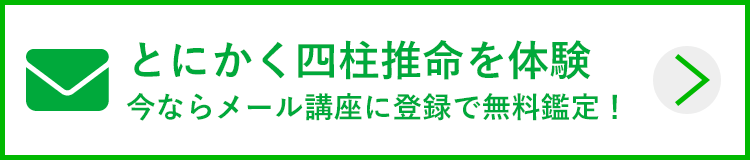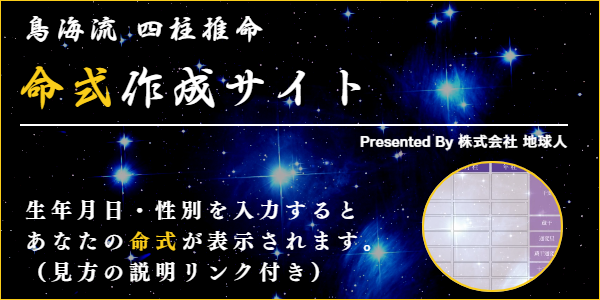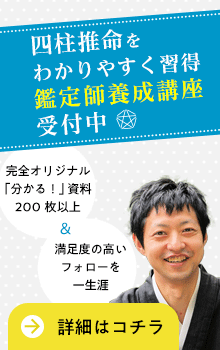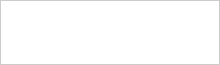穀雨-こくう-(4月20日~5月4日頃)
特徴
田んぼや畑の準備が整い、それに合わせるように、柔らかな春の雨が降る。地上にあるたくさんの穀物に、たっぷりと水分と栄養が溜め込まれ、元気に育つよう、天からの贈り物でもある恵の雨が、しっとりと降り注いでいる頃のこと。この頃より変りやすい春の天気も安定し日差しも強まる。
花『藤』
桜が散ると、藤の季節になります。日本では、藤棚や盆栽に仕立てられることが多く、垂れ下がる紫の花は、周囲の緑に映えて鮮やかさを演出し、人々の心を惹きつけます。
野菜『筍-たけのこ-』
筍はタケ類の地下茎からでる幼茎のことです。「筍」という漢字は、竹が10日間(一旬)で成長するため、竹の旬の時期という意味が由来であるとも言われています
野菜『へびいちご』
名前からして、毒々しいイメージがあるかもしれませんが、毒はありません。果実はきれいな赤色ですが、味がないことから食用とはされていません。
魚『ヤリイカ』
全体的に細長く、地方によってはササイカ、サヤナガ、テッポウなどの呼び方があります。ヤリイカは透明、茶色、白と色が変化していくため、透明のものは鮮度が高いといえます。
行事『八十八夜』
立春から数えて、八十八日目に当たる夜のことです。(5月2日頃)田植えや茶摘みが行われる時期であります。八十八夜に摘んだ茶葉は、長寿の薬ともいわれたそうです。
七十二候
葭始生-あしはじめてしょうず-(20~24日頃)
水辺の葭が芽吹き始め、山の植物、野の植物が緑一色に輝き始める頃。葭は、最終的にすだれや屋根などに形を変え、人々の生活を手助けしてくれます。葭は夏に背を伸ばし、秋に黄金色の穂をなびかせます。
霜止出苗-しもやみてなえいずる-(25~29日頃)
暖かくなり、霜も降らなくなり、苗がすくすくと育つ頃。田植えの準備が始まり、活気にあふれている農家の様子が連想できる言葉です。霜は作物の大敵とされています。
牡丹華-ぼたんはなさく-(30~5/4日頃)
「百花の王」と呼ばれている牡丹が開花し始める頃。美しく、豪華で、艶やかで大きくて存在感があり堂々としている牡丹。中国では、国の代表花として牡丹があげられ、数え切れないほどの逸話や美術に登場します。
![四柱推命をどこよりもやさしく学ぶ 四柱推命 講師の書 [人を幸せにできる人を、日本中に増やす]](http://suimei.hpjt.biz/blog/wp-content/themes/biz-vektor/v2/img/head/sp_title.gif)
![四柱推命 講師の書 [人を幸せにできる人を、日本中に増やす]](http://suimei.hpjt.biz/blog/wp-content/themes/biz-vektor/v2/img/head/title.png)